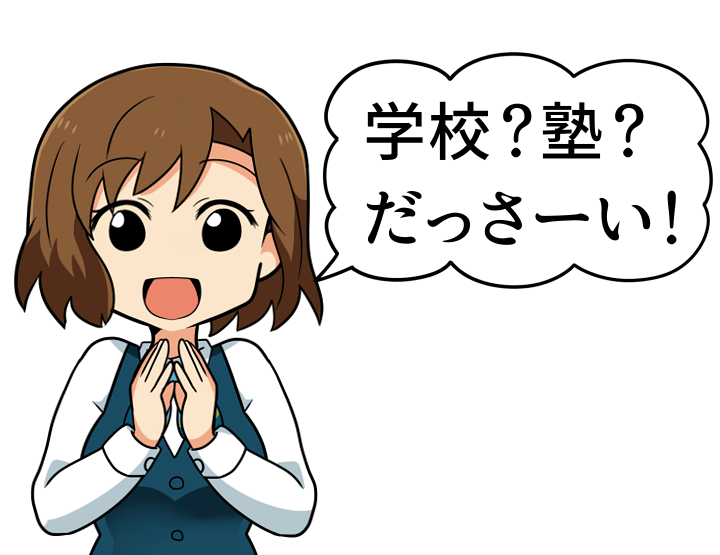
皆様、いかがお過ごしでしょうか。毎度、さっちゃ~んでございます。
ワイは、英語大嫌いなんですが、
この英語嫌いというのは、この日本における受験制度とワイに英語を教えてきた教師どもの教育レベルの低さじゃないか?という仮説を思い浮かびましたのね
今一度、英語の根本的な部分を学び直そうという記事になります。
作成してて思ったのは、やはり学校という教育システムと教育する側の質の悪さが原因ですね。
というわけで、皆様、英語大嫌いだと思いますが、暇つぶしに読んでみてはいかがでしょうか。
受験勉強をする学生は絶対知っておきたい英語の知識で、これ理解してなかったらいくら英語の勉強しても無駄と断言しましょう。
学生の方だけではなく、意識高い系ニートが、TOEIC受けるといった時でも必修になります。
英語の歴史
英文法を学ぶ上で、なぜ格文法のルーツを知ることが重要かというと、これを抑えることで、頭の整理が格段に上がるからです。
英語はゲルマン語やラテン語など、多種多様な言語が混ざり合ってできた言葉です。そのため文法のルールに規則性がないことが多く、学んでいて混乱しやすくなっております。
歴史をたどると英語は現在のイギリスの本当にあるグレート・ブリテン嶋に様々な民族が移り住んできたことで、数多くの言語の文法や単語を取り入れながら変化していきました。
英語は大きく変化した時期に着目すると4つに分けられます
1古英語
今から約1500年前、英語発祥の国であるイギリスの本島であるブリテン島に、ゲルマン民族が移住してきたことがきっかけとなりました。
5世紀ごろまで、ブリテン島にはケルト民族のブリトン人が住んでいました。
そこへ、現代のドイツ人に通じるゲルマン民族の一派が進攻を開始したのです(ゲルマン人の大移動)。
このとき、この島で以前から話されていたケルト語と、新たに入ってきたゲルマン語が混ざり合ってできたのが英語の起源である古英語となります。
古英語は、アルファベットも現在と異なるほか、地方ごとに文法や単語が定まっていませんでした。
現代の英語とはかけ離れた言葉なので、私たち日本人にとっての平安文学のように、理解するには勉強が必要になります。
2中英語
古英語にラテン語が混ざり合います。1066年フランス北部にあるノルマンディー地方の君主が、ブリテン島を征服してイングランド王に即位しました。このとき、それまでブリテン島で話されていた古英語と、ノルマンディー地方の人が話していたラテン語がぶつかり、中英語が成立しました。
ラテン語は、ポルトガル、スペイン、フランス、イタリアなど、もともと神聖ローマ帝国の勢力圏で話されていた言語です。当時、ブリテン島にやってきたのは、ラテン語からフランス語へと変わる過渡期の言葉でした。
3近代英語
1600年代に入って文法や単語が洗練され、現代の英語に非常に近い形になったものを指します。
大航海時代を経て、キリスト教の布教を目的として中英語の文法や単語が統一され、1900年代初頭までほぼ同じ形式で使用されました。
4現代英語
近代英語はもともと布教のためにまとめられた英語だったため、形式的な表現が多いという難点がありました。
20世紀に近づくと、タイタニック号が象徴するような巨大客船などによる大量の移民が英語圏に流入します。
さらに、第二次世界大戦後、アメリカが戦勝国として世界経済をリードするようになると、世界中の人々が英語を使ってビジネスを始めます。
英語圏が急速に拡大して外国との国際的な交流が活発化する過程で「英語の簡略化」も急速に進みました。
英文法を学ぶ上では、この「英語の簡略化」が大きなキーワードとなります。
似たような表現の単語が統一されたり、文法の一部が省かれた英語へと変化したりしました。これが、私たちが学ぶ現代英語です。
英語の構造
英語に置いて最重要なのは「動詞」と「文型」です。英語の基本構造というのはこの2つの要素が9割以上を占めています。
次に「冠詞」「前置詞」など「名刺や動詞を周辺で支える文法」最後に「接続詞」「形容詞」「副詞」です。
何故「be動詞」と呼ぶのか?
皆さんは、英語の先生にこの質問をすると先生は「そういうものだから.....」と回答するでしょう。
なんで、英語知らない奴に英語教わっているのかわからなくなりますよね
この疑問の答えは「be動詞」が歩んできた歴史にあります。
「be動詞」の起源は、古英語までさかのぼります。
am-béo are-bist is-biþ
「be動詞」というのは、これらの語幹の「b」と、最も使用頻度の高い一人称表現の「béo」から名付けられたものです。
「be動詞」の活用がバラバラなのは「それぞれ違う語源を持ち、時代を経て変化した」英語の歴史の賜物になっています。
amとis、wasはインドのサンスクリット語「asmi」「asti」「vasati」
areは古北欧語の「art」
wereも古北欧語で「wesa」「wesan」
英語は「インド・ヨーロッパ語族」というグループの一つで、インドやヨーロッパで話される言語と近い祖先をもちます。
「be動詞」には、①性質(変わらないもの)②状態(そのときの一時的な状態)③所在(人やモノがどこにあるのか)という「隠れニュアンス」を持っていて、実はこの3パターンだけで「be動詞」は全て説明できるようになっています。
なぜ「三単現」だけ動詞にsがつくのか?
一般動詞では「三人称・単数・現在の場合、語尾にsをつける」ルールがあります。
じつは、古英語や中英語では、主語に合わせて動詞が全て変化していました。これは決して珍しいことではなく、現代のヨーロッパ言語も同様に、現在形であっても全て主語によって同氏は変化します。例えばスペイン語を覚える時は、1つの動詞につき、現在形だけで6種類(一人称・二人称・三人称・一人称複数・二人称複数・三人称複数)の活用を覚えなくてはいけません。
動詞を覚えるのが非常に大変ではあるものの「動詞を活用することで、主語を省略できる」というメリットがあります。
このようにヨーロッパ言語では、古代から現代にいたるまで、動詞を活用させて主語を省略するという特徴があります。
ではなぜ、現在の英語は「三単現にs」に至ったのか?
他のヨーロッパ言語とは逆の考え方をしました。
つまり英語は「主語を話すことで、動詞の活用を省く」という方向で変化したのです。
その一方で会話でよく登場する「三人称・単数・現在」だけは、強調した方が分かりやすいということで、様々な活用方法の中から「語尾にsをつける」という最小限の活用形で残ったと考えられています。
「be動詞」と「一般動詞」の使い分けのコツ
・He is in bed.
・He sleeps in bed.
これはまず「情景(静的)か動的(積極的)か」という認識でbe動詞と一般動詞を分けて、それから単語を選ぶという考え方をしています。普段の会話では、動詞を使うだけで特に問題はありませんが、より正確にbe動詞と一般動詞を使い分けたいと思う場合は、「静的か動的か」という視点で考えることとなります。
一般動詞の否定文・疑問文で「do」が登場する謎
They come here today.
They do not come here today.
Do they come here today?
このように否定文や疑問文で、突然doが登場するの?という疑問を抱いた人は少なくないと思います。
実は古英語から近代英語までは肯定文でも「do」が使われていました
They do come here today.
現代英語でこのような形を使用する場合「京、彼らはここに間違いなく来ます」と、動詞の「come」を強調する表現になります。
しかし、近代英語までは「do+動詞の原形」がワンセットで動詞だったのです。
じつは、「be動詞」と同じルールで否定文と疑問文が作られていっただけなんですね。「否定文・疑問文で登場するdo」は、決して突然出てきたものではなく、肯定文で隠れていたdoが、be動詞のルールと同じように移動した者ということだったわけです。
これは、does、didでも考え方は同様になっています。
かつての英語で「do come」「do swim」等と使われていた理由は諸説ありますが、「動詞の原形を名詞扱いしていた」と捉えることができます。
「5W1H」の中でHowの頭文字だけHなのか?
現在「wh」で始まる疑問詞は、古英語の時代は「What」「hwo」「hwu」とすべて「hw」から始まる単語でした。このつづりが変化するのは、ノルマン人が侵攻して形成された中英語の時代です。
ラテン語系の人々がブリテン島に流入してくると、古英語の綴りの一部で変更が発生しました。その中で「hwat」はwhat、「hwo」はwhoへと変わっていったのです。
もともと、フランス語などのラテン系の言語では、hを発音しませんでした。
そのため、hwatやhwoといった「hwで始まる疑問詞」が発音しにくかったです。
そこで、wとhを入れ替え、whatやwhoと書くようになったというわけです。
一方、現在のhowにあたる「hwu」は、古英語が定着する前の古いゲルマン語などに由来しています。
後にブリテン島にきたノルマン人は、やはりhを発音しないたいめ、当初は「うー」と発音していました。それが時代と共に「ハウ」のように変化していき、変化した発音に合わせて語尾にwをつけ「how」と書かれるようになったのです。
このような名残は、現在の英語とフランス語の愛でもよく見られます
例「theater」シアター→フランス語「theatre」シアトル
英語は順番が命
日本語というのは英語と違って「助詞」を持つ特殊な言語です。そのため、日本語の場合、単語の順番を入れ替えたとしても意味が伝わるようになっています。
「助詞」という機能が存在する言語は、ざっくりいうと日本語か韓国語くらいしかなく、日本語というのは世界的にみて非常に珍しい言語と言えます。
では、なぜ英語には助詞が存在しないのに、主語や目的語が分かるのでしょうか?
それは「英語は『単語の順番』で主語や目的語を決めている」からです。
He ate an apple.
→An apple ate him.
→Ate he an apple.
このように英語は順番が命であり、順番が違うと意味は全く伝わらなくなってしまいます。
英語は基本的に1番目の単語を「主語」、2番目の単語を「述語」と認識する形の文です。
日本語の場合は「~は」や「~を」があるため、順番はそれほど重要ではありません。
しかし、英語の場合は女子がないので、順番で主語と述語を決めるというルールになっています。
英語には「主語と述語が先」の原則から分かるように「先に出した単語がより重要」という隠れニュアンスがあります。
ここに英語の文法で最初にやる「5つの文型」をやる意味合いがあったわけです。
前置詞
そもそも前置詞とは、その漢字が指す通り「前に置く言葉」です。
じゃあ、何の前に置くかといえば「名詞」となり「名詞の前に置く言葉」が前置詞の本島の定義となります。
前置詞を使う上で知っておきたいのが、人物に対して使う場合です。
with me、for himのように、人物が「目的格」という形に変化します。
では、なぜ前置詞の後ろは目的格となるのでしょうか。
第3文型に「I meet her.」という分がありました。
このときのherは、meetという動詞の目的語(~に)となっているため、目的格としてherに変化しています。
前置詞を使った文型と言えば、第4文系の目的語が入れ替わる形があります。
I bought her a ring.
I bought a ring for her.
通常の第4文型の目的語を入れ替える際は、間接目的語のherに」前置詞をつけて目印にします。
until(till)とbyの使い分け
untilとbyの場合、どちらも「~まで」と和訳されるので混同しがちです。
では、ネイティブではどうやって両者を使い分けているかというと、和訳では省略されやすい隠れニュアンスによってです。
厳密には、untilは「~までずっと」という継続の意味で使われ、byは、「~までには」という期限の」意味で使われます。
toとtowardの使い分け
toの場合「~を目的地に」という隠れニュアンスがあり、一方、towardは「~の方面に」という意味を表します。
I go to Tokyo.(私は東京に行きます)
I go toward Tokyo.(私は東京の方面に向かいます)
belowとunderの使い分け
日常生活で良く使われるbelowとunderは「~の下に」と訳されるので使い分けが難しい前置詞です。
belowが「~の下のほうに」と位置をやんわりと示すニュアンスなのに対し、underは「~の真下に」とより限定した言い方なのが特徴です。
fromの隠れニュアンス
fromといえば一般的に「~から」という意味で教わると思います。
この意味でも大抵通じるのですが「~から」だけで理解していると対応できない場面があります。
fromの隠れニュアンス「~から(離れる)」です。
例えば
Your opinion is different from mine.
これも本来のニュアンスでは「あなたと私の意見は違っていて、離れている」という雰囲気を持つわけです。
fromの隠れニュアンスは、日本語にない概念なので、和訳するのはほぼ不可能です。
日本語としては違和感の」ある分になってしまいます。
He is absent from school.
~を欠席するという意味で良く登場するフレーズですが、これも「彼は学校を欠席して、学校から遠ざかっています」となり、これを意訳して「学校を欠席しています」ということになります。
aboutの隠れニュアンス
なぜ「~について」と「約」が同じaboutかというと、隠れニュアンスの「~辺り」を含んでいるからです。
talk about ~について話す/be about 約~いる/walk about ~を歩き回る/come about ~を旋回する
接続詞のルール
接続詞の定義は「文と文をつなぐ言葉」ですので、接続詞のあとにすぐ「,(カンマ)」をつけてはいけません。
例外として、howeverやthereforeは、副詞から発生した単語です。
接続詞を置くとき、文章として、前側に置くか文中に入れるか、これは何故そんな使い分けされているのか疑問に思うことあったと思いますが、これはどちらでも構わないからです。
ただ、文中に「強調したしたい方を前に置く」ということをしているだけになります。
間違いやすい接続詞~の間
ここで紛らわしいのがduringとwhileですが、duringは前置詞でwhileは接続詞であることに注意しましょう。
なんで英語の時制はこんなに細かいのか
「時制」で一番大切なのは「点時制」と「線時制」を分けて理解することです。
時制が苦手な人は、「日本語と共通する点時制」と「日本語には存在しない線時制」を混ぜて覚えようとして混乱していることが多いようです。
実は時制こそ「理解する順番」がとても大切です。順番を間違えてしまうと一巻の終わりです。
まずは「日本語と共通する点時制」について「現在形」→「進行形」→「過去形」→「未来系」と、日常で使う頻度の高い文法から順番に理解していくことがポイントとなります。
次に「日本語に存在しない線時制」です。学校では「公式の暗記」で処理されてしまい、ネイティヴが感じ取っている「時間の感覚」を理解する作業が抜け落ちてしまっています。
「線時制」を学ぶときは、まずネイティヴが感じ取っている「時間の感覚」をきちんと理解することが大切です。
「時間の感覚」を理解するためには、やはり日常で使用する頻度が高い順に「現在完了形」→「過去完了形」→「未来完了形」→「完了進行形」と学んでいくと、私たちの生活の出来事とリンクしやすく、理解しやすくなります。
最後は「神様の時間」です。英語には「神様の時間」という特別な時間帯があります。この時間帯は、歴史や宗教観を元に解釈する必要があります。この解釈ができると、高校時代に「超難解」と言われていた「仮定法」や「敬語」「条件副詞節」が不思議なほど一瞬で理解できてしまうのです。
英語の時制は15種類あります。一方で日本語の時制は6種類の身です。そのため、日本人が英語の文を話そうとする場合、日本語の倍以上の時制を意識しないといけません。
英語の時制は「もし~なら」という仮定の話をする「仮定法」と通常の文である「直接法」の2つに分けることができます。
直接法とは、仮定法以外の通常の文の時制を扱う文法で、ある一点の時間帯を起点とする点時制と、一定期間の時間帯を起点とする線時制という2種類に分かれます。
点時制と線時制の大きな違いは、中学校で習う「完了形」を使うのが線時制で、「完了形」を使わないのが点時制です。
英語の時制が難しいと感じる理由はもう一つ、時制が感覚的に掴むものだからです。
私たちの頭の中には「今、このあたりの時間帯を指しているな」と、時制を感じ取るセンサーがあります。
時制という概念は、理屈よりも、この頭の中のセンサーで感じ取って使う必要があります。
つまり、完了形など日本語にない時制というのは、私たち日本人にとって「感覚的に理解できない時制」であるため、使いこなすのが非常に難しいわけです。
完了形や未来形などの文法の公式を覚えているのに、中々正しく使えない人が多いのは、日本語と英語の「時制感覚の差」という落とし穴があるからです。
現在形
現在の時間以外も扱い用法は4つ
・確実な未来(少なくとも自分は必ず起きると信じている時)
・現在を含む行動・現在の状態
・よく起きること、習慣
・不変の真理
現在形とはいいつつも、現在以外の時制が入っているので非常にややこしいですが過去形で詳しく説明します。
進行形
ネイティブにおける進行形の感覚は「その瞬間、何をしているのか」という一点だけを切り取った表現です。
たんに「~している」と解釈すると「一定期間の長さが必要だ」と間違った解釈が発生します。
この進行形が「点時制」のグループに位置しています。
過去進行形・現在進行形・未来進行形
過去形
過去形とは2つのことを指します
・ある過去の「一点」で起きたこと
ここでいう「一点」とは、進行形の場合はより狭い「ある瞬間」を指しているのに対して、より広い「過去のある時点」を指しています。
・漠然とした過去の一定期間
「一定期間というと、完了形のような線時制ではないか?」という疑問を持つ人もいるかもしれませんが、「始まり」や「終わり」をはっきり表現しない場合に過去形が使われます。
英語の場合は「いつまでの期間なのか」という情報がないと線時制の完了形ではなく、点時制の過去形が使われることになります。そういった意味でも先程の現在形と似ていますね。
また過去形の動詞に関する「規則動詞」と「不規則動詞」に関して説明します。
じつは、古英語から中英語までの時代、すべての単語が「不規則動詞」だったのですが、戦争などで移民が増えて、様々な民族が英語を使うようになると、これまでに何度も紹介した英語特有の「簡略化」が進みます。単語の不規則変化は、方言のように地域ごとの独自なものがあるなど、複雑になっていたため、不規則な過去形が複数あるような単語は、すべて「~ed」で統一することにした、という歴史があるわけです。
このような動きは、ある特定の期間から始まったものではなく、各単語でそれぞれ緩やかに進められていき、長い年月を経て「~ed」の動詞が増えていきました。
日本語で言うと「全然~ない」の「全然」が「全然OK」というように肯定でも使われるようになった感じですね。
未来形
日本語と英語の未来形の違いについては2つの言語の文化的な背景に着目して理解する必要があります。
日本語は、過去に目を向ける文化をベースにしています。平安文学などをはじめとする日本文化は、過去のことを話したり、過去の人物や出来事について偲んだりすることで発展してきた側面があります。
その一方で、英語の歴史はこれまで話してきたように戦争に寄って形作られたという側面があります、その影響で、過去を振り返るのではなく、人々の未来について語ることを中心に小説や言論が発達してきたのです、
聖書などを見ても「こうすれば、このように幸せになれる」というように、未来に目を向ける記述が多い傾向にあります。
一般的に、キリスト教国の多くで、未来に目を向ける文化性が発達したと言われています。英語という言語においても、未来に向ける感性が育ったという見方があります。
日本語における未来は「だろう」「するだろう」の2通りだけですが、英語における未来形は大きく分けて5種類もあります。
1will「自分の意思」「ただの未来」
元々は自分の意思で使われていましたが19世紀から「ただの未来」としても使われるようになりました
2be going to「以前から決まっていた未来」「他人が決めた未来」
「~することに向かっている」という隠れニュアンスがあり、「今この瞬間、~することに向かっている」と現在・未来の複合的な時制を感じることができます。
3現在形「反復動作」
習慣としての反復動作。「明日7時にバスが出発します」といった英文に使います。
ただ、アメリカやカナダなど、複数の英語圏の国のネイティブに、この場合、現在形とwillどちらを使うか聞いたところ半々だそうで、どちらの用法を使っても問題ないでしょう。選択肢としてどちらか選ばせるケースがあったら悪問かもしれません
4ごく近い未来に現在進行形
「もうすぐつくよ!」などと「一瞬」を強調する現在進行形を使います。
5shall
Shall we Dance?もありますが、willよりも強い意思表示の時「必ず~する」「~しなきゃ!」という時に使用します。また、運命的な表現「You Shall die(お前はもう死んでいる)」といった場合は非常に大げさな表現なので、日常英語にはあんまり登場しません。
映画でも「shall」を使っていたら相当強調されていると覚えておきましょう
現在完了形
いよいよ、英語を学ぶ上で意味が分からない用法「現在完了形」に突入します。
「線時制」なので、日本語にはない時制感覚です。
現在完了形の正しい時制は「現在につながる過去」を意味します。
これは「ある過去の一点で発生した状態がずっと続いて、今も続いている」という状態が現在完了形の感覚です。
つまり「have 過去分詞」を使うことで、ネイティブが聞いたときに「過去に起こっていたことが今も続いているんだ」という隠れニュアンスを読み取ることになります。
一方、通常の過去形を使った場合「過去にこういうことがあった」という淡白な表現になり、「(でも今は関係ない、過去のこと)」という隠れニュアンスが相手に伝わります。
現在完了形と過去形には「過去に起きた状況が、現在にも直接関係しているか」という大きな違いがあります。
ここが、英語圏のネイティブが過去にこだわるかこだわらないかを明確に分ける表現を使っているわけですね。
過去は過去とするか、現在完了形にするかを分けることができるから、意識的にも過去を気にしない文化が形成されているというわけです。
haveは持つだけでなく「~してもらう/させている」という使役の意味を持つ動詞です。
過去分詞の形には「~させられる」という受動態の意味があります。
この言い回しの語順を見ると
主語+述語(have)+目的語+過去分詞
となりそうですが、目的語を挟むのは少し回りくどいとネイティブの人は考えたそうです。
そこで使役動詞と過去分詞をまとめてVにすることでSVOの形に近づけました。
由来としては「have 過去分詞を合わせて述語化したもの」ということです。諸説あり
過去完了形・未来完了形
ポイントは「ある一点まで続く期間」ということで、過去完了形「いつから始まったか」はあいまいですが「過去のある一点に終わって、今は違う」という表現になります。未来完了形は「未来のある一点まで続く状態」を指します。
完了形の「線時制」は、時制を「点」で捉えず、「線」でイメージするもので、日本語には全くない概念です。
だから、英語圏の文化は述語がいつまで続いている状態といった「時の状態」というものを非常に大事にするわけですね。
完了進行形
「完了」って言葉がややこしいですが、今も継続して行われているという表現で「線時制」+進行形を加えます。この「線時制」の解釈がないと完了形と進行形が合わさった時ごっちゃになることでしょう。
仮定法の由来・何故現在形なのに過去形を使うのか?
それにしても、仮定法では現在形なのに過去形を使い、主語の後のbe動詞がwereになる。全く意味が分かりません。
仮定法がこのような不思議な用法になったのは英語の歴史にあります。
約1500年前キリスト教徒の普及に伴って、言語として熟成していきます。
キリスト教の聖書は当時英語で書かれておらず、英語圏で普及させるには、英語に翻訳する必要がありました。
ところが「当時の英語には敬語が存在しなかった」わけです。
なぜ、聖書の翻訳に敬語が必要だったかというと、旧約聖書は「神と人」の物語であり、新約聖書は神の子である「イエス・キリスト」の物語です。
旧約聖書には神が人間に罰を与えるエピソードがあり、新約聖書では神の分身であるキリストが様々な奇跡を起こします。
つまり、キリスト教では、神は恐れ敬うべき存在だったわけです。
ヘブライ語やラテン語では、神や王など、尊敬しなくてはいけない人の行動を、人間の動詞とは区別した特別な単語で記述していました。
一方、様々な言語が混ざり合ってようやく成立したばかりの古英語には、そのような特別な動詞などは存在していませんでした。
敬語がないからといって、人間が使う動詞と同じ活用を使って翻訳してしまうと「神と人間を同列にした」ということで、神の怒りを買ってしまうかもしれません。
神罰を畏れた当時の神官たちは「人間と違う動詞の活用方法で、神の行動を翻訳しよう」と考えたのです。
そこで神官たちが注目したのが「時制の変化」です。
人間が神の領域の話をする時は、時制を一段下げることで、自分の立場を下げ、神に対し畏敬の念を示すことにしたのです。考え方としては、謙譲語のような発想です。
つまり、文の本来の時制が現在形なら過去形で、未来形なら現在形で、過去形なら過去完了形というように「動詞の時制を一段下げる」ことで「恐れ多い神の領域」の話をすることに畏敬の念を示す、謙譲語の意味を持たせる習慣が拡がったのです。
キリスト教が普及するにつれ、より英語とキリスト教の関係は密接になり、英語表現への大きな影響を与えるようになります。
「神様にしか実現頂けない話ですが、もし~なら」というニュアンスで話されるひょうになたと考えられます。
英語には敬語の表現は謙譲語(自分を下げる表現)しかありません。
基本的には、日本語のような尊敬語は存在しないと考えてください。
英語では、もともとの文を過去形にすることで、丁寧な依頼を意味する謙譲語になります。つまり、仮定法の考え方に由来するわけです
キリスト教の影響を受けた英語は「神に対する畏敬の念」を表すため二、動詞の時制を下げるというルールを作りました。それが、長い年月を経て使われているうちに、神だけでなく、王に対する謙譲語としても使用されるようになります。
さらに時間が経つと、一般的に偉い人に対する謙譲語へと変化し、最終的に「目上の人の謙譲語」として「時制を下げた表現」が使われるようになったわけです。
つまり、英語の敬語は「自分の時制を下げた表現をする」という考え方だけで、いくらでも応用が可能というわけです。
動詞から派生した文法
助動詞
will
ゲルマン語の「wilijo(意図)」に由来する言葉で、「意思で決めた未来」を指します。
will not の省略形won'tになったのは、説としては発音のしやすさらしいです。willn'tを使っていた時期もあったそうですが、文中に登場すると詰まってしまい、長い間使っているうちに「ウォンと」と伸ばすようになった、というのです。
日本語でも「雰囲気」は「ふいんき」とひっくり返って発音されることが度々あるのと同じ感じです。
can
もともと古英語の「cunnan(知っている)」という動詞に由来しています。
つまり、本来can swimとは「泳ぎ方を知っている(泳ぐ方法が体に染みついている」という意味になります。
その一方「be able to」はラテン語の「habilis(状況的に~することができる)」という単語に由来します。
ただ、英語を第2言語としている人の中では、使い分けできる人はあまり多くないのが実情だそうです。
may
mayの語源はラテン語で、古代ローマの神様である「Maiusマイウス」に由来し、後に「力を与える」という意味として使われるようになります。
マイウスは豊穣をつかさどる神ですが、当時の産業は全て農業に左右されていました。そのため、豊饒の神というのはその国や人に力を授ける存在だったのです。このような背景から「マイウスという力を持つ神の名のもとに、力を与える」というニュアンスでmayが使われるようになりました。そのため「~してもよい」「~かもしれない」「~でありますように」という一見すると共通点のないような使い方をされているわけです。
「~かもしれない」は「神にお願いしたらここに来るかもしれない」という意味が込められています。
過去形のmightは時制下げによってニュアンスを和らげるために使われます。
mightも「力を与える」というニュアンスを含んでおり、形容詞のmightyはstrongなどよりも強い言葉で圧倒的な力があるようなニュアンスで使われます。
almighty(オールマイティ)もall+mightyで「全能の」という意味がある形容詞となります。
must
mustは「自分がしなくてはいけないと思うこと」で、古英語の「motan(自分の意思で~しなければならない」の過去形「moste」からきています。
しかし、We must pay tax.だと「私たちは納税を自分意思でしなければならない」となるので、代用として「have to」が使われるようになりました。
to doだけで「~すべき」という意味があります。「have to do」は「すべきことを持っている」という隠れニュアンスがあるフレーズだったわけです。
またmustの否定は「~してはいけない」となりますがこれは、must本来の意味が「~することを許されている」なので、禁止の意味が残ってしまいました。
本来なら「~しなくてもよい」という意味なので、must notではニュアンスのずれが生じてしまいます。
そのため現代では、否定の際はhave toの否定形の「don't have to~」が一般的に使われるというわけです。
should
「~すべきだ」「~するはずだ」
こちらも神を意識した単語です。
shouldの語源は古英語の「sceal(負っている/義務がある)」です。宗教と生活が非常に密接だった古英語の時代に「(神によって)義務付けられている」ように、宗教的な意味合いを込めて使われていました。
つまり、2つの意味には「神によって義務付けられている」という隠れニュアンスがあります。
つまり「(神によって義務付けられているから)~すべきだ」「(神によって義務付けられているから)~するはずだ」としっかり共通点があるわけです。
またshallの過去形であるshouldは、shallを過去形にすることで意味を弱めています。
shallは「運命的に~することになる」という神を前提にしたニュアンスをやわらげた結果「~するべきだよ」という人間目線での表現に落ち着いたと考えられます。
to 不定詞
これには隠れニュアンス「~に対して」「~に向かって」という意味があり、その後に動詞の原形は、原型だけで「~すること」という名詞として使われていました。
元々は「to 動詞の名詞形」だったわけです。
すると、to不定詞は「~することに対して/向かって」という「前置詞+名詞」がもともとの形だったわけです。
これによって名詞的用法・形容詞的用法・副詞的用法も全部説明できます。
また、主語が一人称でも三人称でも動詞の形が限定されないので「不定詞」と呼ばれています。
be to 構文
be to 構文は英文法の中で最もいい加減な文法で「is toは助動詞として働きます。使い方としてはwill can must shouldのどれかの意味で使います」と教わったらもう最悪です。日本の英語教育は、試験のためという側面が強く、どうしても「1つの正解」を求めがちです。
しかし、言語というのはあくまでコミュニケーションのツールであり、政界が一つとは限りません。
be to構文の始まりは、1066年のノルマン人の征服までさかのぼります。フランス北部のノルマンディー地方の君主がブリテン島南部地域を征服し、ノルマン人が当時のイギリス人を支配下に置きます。通常、戦争の勝者が敗者を支配下に置き、自分たちの言語で相手を支配しますが、ノルマン人が話していた古フランス語は、文法が非常に複雑で、イギリス人に全く普及しませんでした。
このままでは統治が難しいと困ったノルマン人は、文法が簡単な古英語を覚えて、古英語と古フランス語を混ぜながら支配するようになります。これが、古英語と古フランス語が織り交ぜられた中英語が成立した理由です。
そして、同時に出来たのが、このbe to構文です。
支配者層のノルマン人は、被支配者層が使う古英語をまともに学ぶ気がありませんでした。ノルマン人は、going,able,supposedといった単語の使い分けを面倒に感じ、真ん中の単語を省略することを思いつきます。つまり、be to構文はノルマン人の怠慢の産物だったわけです。
なので、beto構文は残念ながら「ニュアンスで読み取る」のが正解です。
分詞
動詞を形容詞として使う時の文法です。
現在分詞:変わらない「性質」
過去分詞:一時的な「状態」
to不定詞は「~することに向かっている」という未来的な隠れニュアンスがあるので、未来のことなど、まだ起きるかどうかわからないことについて語る動詞ではto不定詞となり、動名詞の場合は、「起きることが確定している動詞」として使い分けます。
その他文法
受動態
英語は簡略し続けて現代に至ってはおりますが、能動態を受動態に変える必要性がどこにあるのか?という疑問が浮かんでいきます。
受動態が現代英語でも使用されている理由はじつは「責任逃れのため」であります
He broke the window.
The window was broken by him.
英語には大事なことを最初に置くという原則があります。この原則に伴って能動態の文をみると、主語に当たるHeが最も強調された大事なことであるということになります。
能動態の目的語を主人公にすることで、元主語をぼかしたいという心理が受動態となります。
The window was broken.
こうすれば、行動主をぼかすことができます。
まとめ
皆さんの学校の英語教師のレベルがどうかはわかりませんが、ワイの学生時代の時の英語教師は中・高ともにレベルが低かったので、こういう根本的なことは知りませんでした。
世の中って環境によって決まりますね。








